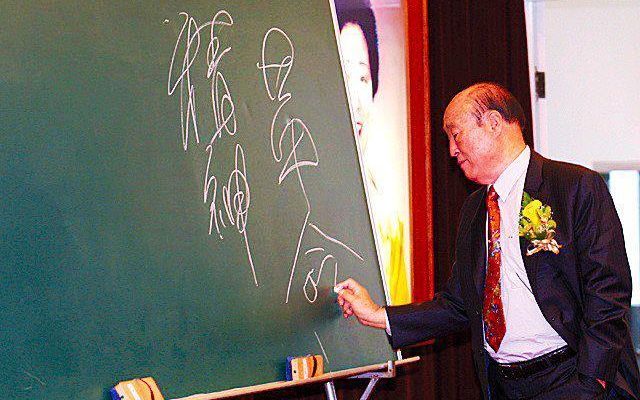
やると言えばやる「一日泣き」の強情っばり
父はお金を貸して踏み倒されることはあっても、返してもらうことには無頓着な人でした。しかし、自分がお金の入り用があって借金したときは、返済の約束は、牛を売り、家の柱を抜いてでも必ず守る人でした。父はいつも、「小手先の企みで真理を曲げることはできない。真というものは、そんな企みに屈するものではない。小手先の企みで何をしようと、数年も経たずにぼろが出るものだ」と言っていました。父は風采が良かったばかりか、米俵を背負って階段をのっしのっしと上がっていくほど逞しい体の持ち主でした。私が九十歳(数え)になっても世界を股に掛けて活動できるのは、父から譲り受けた体力のおかげです。
讃美歌「あの高い所に向かって」を好んで歌った母も、並の女性ではありませんでした。真っすぐで、豪胆で、荒っぽいのが母の性格でした。額や頭のつるりとしたところに加えて、性格もそのまま受け継いだ私は、我が強く、この母にしてこの息子ありと言えそうです。
幼い頃、私のあだ名は一日泣き」でした。一度泣き始めると、一日中泣いてようやく泣き止むところから付いたあだ名です。泣くときは、一大事でも起こったかのようにわんわん泣いて、寝ている者が皆起き出してくるほどだったといいます。じっと座って泣いたのではありません。部屋の中で、ひっくり返って、跳ね回りながら騒ぎを起こして、体のあちこちに傷ができ、皮膚が切れて、部屋のそこらじゅうが血だらけになるほど泣いたそうです。幼い時からとても気性の激しいところがありました。
一度決心すると絶対に譲歩しませんでした。どんなことがあっても譲歩しませんでした。もちろん物心がつく前のことです。過ちを犯したのは私だと分かっていても、母が何か指摘すると、「違う。絶対違う1」と言ってぶつかりました。「間違っていました」と一言で済むのに、死んでもその言葉を口にしませんでした。しかし母も負けてはいません。「さあ、親が答えなさいというのに答えないのか!」と言って叩くのです。ある時などは、何回叩かれたか分からないほど叩かれて気絶してしまいました。それでも私は降伏しませんでした。すると今度は、目の前でおいおい泣き始めるではありませんか。その姿を見ても、まだ間違っていたとは言いませんでした。
我が強いだけに勝負欲も強くて、どんなことでも、死んでも負けるものかという気持ちでいました。大げさではなくて、「五山の家の小さな目。あいつは一度やると言ったら必ずやる奴だ」と村の大人の誰もが認めるほどでした。何歳の時だったか、私に鼻血を出させて逃げていった子供の家に一月も通い詰めたあげく、その子と会って、親からは謝罪を受け、餅まで一抱えもらってきたのを見て、大人たちも舌を巻きました。
だからといって、気力だけで勝とうとしたのではありません。同じ年頃の子供たちよりもはるかに体も大きく、力も強かったので、村には腕相撲で私にかなう者がいませんでした。ところが、三歳年上の子に相撲で負けたことがあり、その時はひどく腹が立って我慢がなりませんでした。そこで、毎日山に登り、アカシアの木の皮が剥がれるほど木にぶつかって稽古し、力を付けて、六カ月後にはその子に勝ってしまいました。
わが家は子供が多い家系です。私の上に兄が一人、姉が三人、下に弟と妹が八人いました。幼い頃は兄弟が多くいて、本当に良かったと思います。兄弟姉妹、いとこ、またいとこ、全員呼び集めたら何でもできました。それでも歳月が過ぎてみると、広い世界に私一人が残った気分です。
一九九一年末、北朝鮮に八日間ほど行く機会がありました。四十六年ぶりに故郷に行ってみると、大勢いた兄弟と母はすでに亡くなり、姉一人と妹一人だけが生きていました。子供の頃、母のように私の世話をしてくれた姉は七十を過ぎたお婆さんになっていたし、あれほどかわいかった妹もすでに六十を過ぎて、顔は雛だらけでした。
あの頃は、この妹をなんだかんだとよくからかったものです。「孝善、おまえの新郎になる奴は目が一つしかないそ!」と言って逃げると、「何ですって!そんなこと、お兄さんがどうして分かるの?」と言いながら追いかけてきて、小さな拳で私の背中をパンパン叩きました。十七歳になった年に、孝善が叔母の紹介で見合いをしました。その日、朝早くから起きて、髪をきれいに整え、美しく化粧した孝善は、家の内外を掃除して新郎となるかもしれない人を待っていました。「孝善、おまえそんなに嫁に行きたいのか?」とからかうと、化粧した顔が赤く染まって、その姿が何とも言えずかわいらしかったです。
北朝鮮を訪問して十数年が過ぎた今は、あの時私と会って、胸が痛くなるほど泣いた姉も亡くなり、妹一人が残っているだけというのですから、切なくて、心がすっかり萎れてしまうようです。
手先が器用だった私は、靴下や服の類は自分で編んで着ていました。寒くなれば帽子もすいすい編んで被りました。編み物の腕前は女たちよりも上で、姉にも教えてあげたし、孝善の襟巻きも私が編んでやりました。針仕事も好きでした。熊の足裏のように大きく分厚い手で、下着も自分で作って着たのです。「荒織りの木綿」を置いて、それをさっと半分に折って、型を取って寸法に合わせて裁断した後、裁縫をすると、自分の体にぴったりのものができました。母の足袋もそうやって作って差し上げたところ、母は「おやおや、二番目の子が遊びでしていると思ったら、母さんの足にぴたっと合ってるね」と言って、喜んでくれました。
孝善の下には妹が四人もいました。母は十三人の子供を産んで、五人の子供に先立たれています。母が憔悸したのは言うまでもありません。生活に余裕がない上、子供がそんなにも多くて、母は言葉で言い尽くせないほどの苦労をしました。
その当時、娘を嫁に出すとか嫁をもらうときには、木綿を織らなければなりませんでした。綿花から取り出した綿を糸車に入れて糸を紡ぎますが、糸車に入れる際のほぐした綿の固まりを平安道の言葉で「トケンイ」と言います。子供たちが一人、二人と結婚するたびに、「荒織りの木綿」のように柔らかく美しい木綿が、母の厚ぼったい手を通して作られました。人1 倍手際が良くて、普通の人が一日に三、四枚織る布を、母は十枚も二十枚も織り出しました。姉を嫁に出すというので、速いときは一日に一疋(二反)織ることもありました。決意すれば何でもさっとやってしまう母の性急な性格によく似て、私も何でもさっとやってしまう性分です。
今もそうですが、私は幼い頃からどんな食べ物でもよく食べました。トウモロコシもよく食べ、生のキュウリもよく食べ、生のジャガイモや空豆もよく食べました。二十里(約八キロメートル) 離れている母の実家の畑に蔓が伸びているのがあって、何かと尋ねてみたら「チクァ」という返事でした。その村ではサツマイモを「チクァ」と言ったのです。掘って食べてみると、後味が素晴らしく良くて、籠に入れて持ってきて一人で全部食べました。翌年からは、サツマイモの季節になると、しばしば母の実家に走って行きました。「お母さん、しばらくの問どこそこに行ってきますよ」と言って、二十里の道を一息で走って行き、サツマイモを食べたのです。
故郷では、五月はジャガイモの蓄えが底を尽きかける一番大変な時期です。冬の間はずっとジャガイモばかり食べて、春になって六月頃に麦を収穫するとジャガイモ暮らしは終わりを告げます。麦は最近のように食べやすくした平麦ではなく、丸麦でしたが、それなりに美味しく食べました。丸麦を二日ほど水でふやかしてご飯を炊くと、スプーンでぎゅうぎゅう押さえたとき、飯粒が弾けて散らばります。それにコチュジャン(唐辛子みそ)をさっと混ぜて一口食べると、麦が口の端からしきりに飛び出してきます。そこで、口をむっと閉じて、もぐもぐと食べた覚えがあります。
アマガエルもたくさん捕って食べました。昔の田舎では、子供たちが麻疹にかかるか病気になるかして顔がやつれていれば、アマガエルを食べさせました。太ももがぱんぱんに張った大きなアマガエルを三、四匹捕まえて、カボチャの葉に包んで焼くと、蒸し器で蒸したようにふかふかしてとても美味しいのです。味からすればスズメの肉、キジの肉にも劣りません。広い野原を飛び回っていたクイナはもちろん、まだらでかわいい山鳥の卵もたくさん焼いて食べました。このように、自然界には神様が下さった食べ物があふれていることを、山や野原を歩き回って知っていきました。
平和を愛する世界人として(単行本)文鮮明師 自叙伝 購入はこちらから

