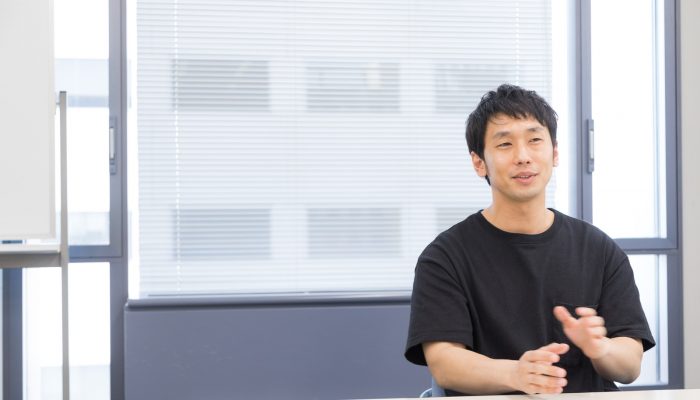
語り部という歴史の証言者
今は文字からビジュアルなメディアへ移行し、新しい視覚的なツールとして、スマホやインターネットで数多くのビジュアルな表現が生まれている。
といっても、その伝達の基本になるのは文字であり、それが簡略化された絵文字であろうが、何であろうが、文字的なツールは決して無くならないだろう。
将来は、あえて文字として表現しなくても、人間同士がテレパシーのように感情を伝達できるような、文字を介在しないコミュニケーションが生まれるかもしれないが、それにしても、知識や文化、技能などの伝承や蓄積という面を考えれば、次の世代へつなげる媒介としての言語・文字というものは必要不可欠である。
たとえば、現代に残された文化資産(ギリシアのパルテノンのような歴史的な建築物)にしても、それだけが残されていても、何の施設かどのようなイベントがそこで行われていたかを確定するのは、考古学的なアプローチだけでは難しいだろう。
それを調べるためには、文字資料、特に神話や文学(詩や神話、悲劇や喜劇の脚本)などの文字で書かれた当時の資料が重要な手がかりになるといっていい。要するに、次世代を意識すれば、文字による伝達は必ず無くならないし、その部族や氏族だけではなく、宗教や文化の違う第三者に伝えるとすれば、客観的な判断の材料となる文字というツールは、無視できない。
とはいえ、文字がなかった時代、それでも、どのようにその種族や氏族の伝承文化を次の世代に伝えていたのか。それはおそらく、口頭による伝言ゲームのように、言葉として記憶し継承していたことは間違いない。
その役割を担ったのが、「語り部」という存在である。要するに、紙に書かれた文字に代わって、言葉を記憶しそれを求められれば口頭で引き出す人間書庫、言葉による歴史や文化の伝承者ということになる。
語り部というのは、その部族や種族の歴史や重要な伝承を次代につなげるための書記官のような役割を果たしていたということができる。
語り部の問題点は、その当事者が病気や何等かの事故によって死んでしまえば、それまで蓄積されてきたその氏族や民族の伝承が失われてしまうことである。
そのリスクを考えれば、文字を媒介とした記録は、その資料を写すことで、そのリスクを避けることができるメディアである。もちろん、書き写すという行為によって、写し間違い、単純なケアレスミスから、意図的な改ざんというリスクも存在するが、語り部の死とともにすべて失われてしまうという事態は避けられる。
この語り部は、日本古代において活躍したことはよく知られている。代表的な存在が、古事記編纂の時に口述を担当した稗田阿礼(ひえだのあれ)という語り部である。稗田阿礼が習い覚えて来た日本古来の歴史伝承を、聞いていた太安万侶(おおのやすまろ)が筆記し、漢字の文章としてまとめあげた。
その意味では、古事記はかなり知識人だった太安万侶の主観や知識が反映されていて、伝承そのものがそのまま伝承されたとは考えにくい。おそらく、編纂を命じた天武天皇の意思が反映された記述になっているはずである。
その上に、この古事記が作成されるにあたっては、多くの氏族から資料を出させ、それを参照しつつ、というよりも、大和朝廷に不都合な伝承や記録はそのまま抹殺されていったり、書き換えられていったということもあり得る。
この点は、文字資料は、政権の意図的な収集によって失われてしまう可能性があることは間違いない。当時の文字資料は木簡や貴重な紙を使ったものだとすれば、どこかに秘蔵しないかぎり、容易に無くなってしまう。
ただ、古事記と時間を置かずに、日本書紀が編纂され、こちらの方には、古事記になはない異伝や資料が加えられて記述されているので、古事記の時に朝廷に差し出された資料を写したコピーや伝承を氏族が隠しもっていたことが考えられる。
伝承や氏族の歴史は、その氏族のアイデンティティーそのものであり、それを無くすことは先祖に対する罪、宗教的禁忌のようなものだったのではないか。
それが天武天皇が崩御したのち、日本書紀の編纂時に現れたのは、当時の政治体制が天皇を中心とした中央集権体制から、氏族の有力者を交えた連合政権的な合議体制に変わっていったからではないか。
あるいは、氏族の伝承を伝えている語り部たち(各氏族に語り部という職掌の者がいたことは明らかにされている)が、大国の唐や朝鮮半島の強国新羅などの脅威に対抗するために、各氏族の対立を避け超国家的な規模の国(律令国家)を建設するにあたり、語り部が召集され、それで対外向けに日本国独立宣言的な日本書紀編纂に当たったのではないか。
いずれにしても、語り部たちは、文字時代にもしばらくはその役職を担っていったが、いつのまにか歴史の闇に消えていってしまった。
と思っていたら、作家の司馬遼太郎が現在も生きている語り部について述べている文章を読んだ。その「生きている出雲王朝」(『司馬遼太郎が考えたこと1』新潮文庫)は、次のように始まっている。
「カタリベというものがある。いまも生きていると知ったとき、私のおどろきは、生物学者がアフリカ海岸で化石魚を発見したときのそれに似ていた」
司馬の言う「カタリベ」というのは、もちろん、現代社会に生きていて表面上は普通の人と変わらないが、その家系が古くまでさかのぼることができる伝承を伝えている人物のことを言う。
要するに、生きた亡霊のようなものだが、なぜ「カタリベ」として今も秘密を守りながら代々子孫に伝えているのかという問題がある。司馬によれば、その人物は自分が勤めていた新聞社(産経新聞)の同僚の記者で、出雲王朝の秘密を代々一子相伝で伝えているのだという。
その伝承には、秘密があって他に漏らしてはならない禁忌になっているので、その内容については、明らかにされていない。
ただ、その概要として記されているのは、出雲王国の主であった大国主命(おおくにぬしのみこと)と大和(天孫降臨に代表される天孫族)の間に行われた「国譲り」神話が、文字で記されているような平和的な禅譲のような政権移行ではなく、血塗られた戦争や弾圧を背景にした武器をもった戦争であったということだろう。
大国主命を祭る一族であった「カタリベ」は、大和王朝の支配下で、本当の歴史を伝えるべく、決して知られることがないように、一子相伝で、しかも絶対に秘密の伝承として長年伝え続けた。時代が変わっても、その伝統は守られ、今後も守られつつ、未来へ向かっていく。
これが本当のことであれば、「カタリベ」は、何のために秘密を守り続けているのか。もはや大和であろうが出雲であろうが、古代時代の対立が終わったはずなのに、と考えるのは、過去と現在が関係のないものとして、歴史を見つめて判断する現代人の傲慢かもしれない。
この滅んだ出雲王朝の「カタリベ」にとっては、滅ぼした大和朝廷への恨みは忘れることができない呪縛であり、過去はDNAのように、現在まで尾を引いている現実なのである。
(フリーライター・福嶋由紀夫)

