
東京砂漠という言葉があったが、今では使う人があまりいないかもしれない。
人はたくさんいるけれども、知人友人もなく、そして隣近所の関係も希薄である。
そういった状態を指した言葉だったが、今では死語に近いかもしれない。
当時はそれがまだ少し珍しく新鮮であったのだろうが、今や東京が砂漠であることは当たり前になっている。
今更、そう表現をする必要もないほど、孤立した関係になっている。
独居老人の孤独死などというものは、「砂漠」だからこそ起こる。
これがまだ濃密な地域交流がある地方であれば、親族や地域社会の関係がまだ残っていたので、砂漠化しつつあっても、まだ緑のオアシスがところどころに点在していた。
しかし、現在では地方の砂漠化も進展し、人間関係が都市部並みに希薄なっているのではないだろうか。
地方でも孤独死が増えている気がする。
東京砂漠と言われた時代、私は大学に入学するために上京し、そしてアパートに下宿しながら、学校に通っていた。
だが、なかなか友人もできず、孤独感を深めたことを覚えている。
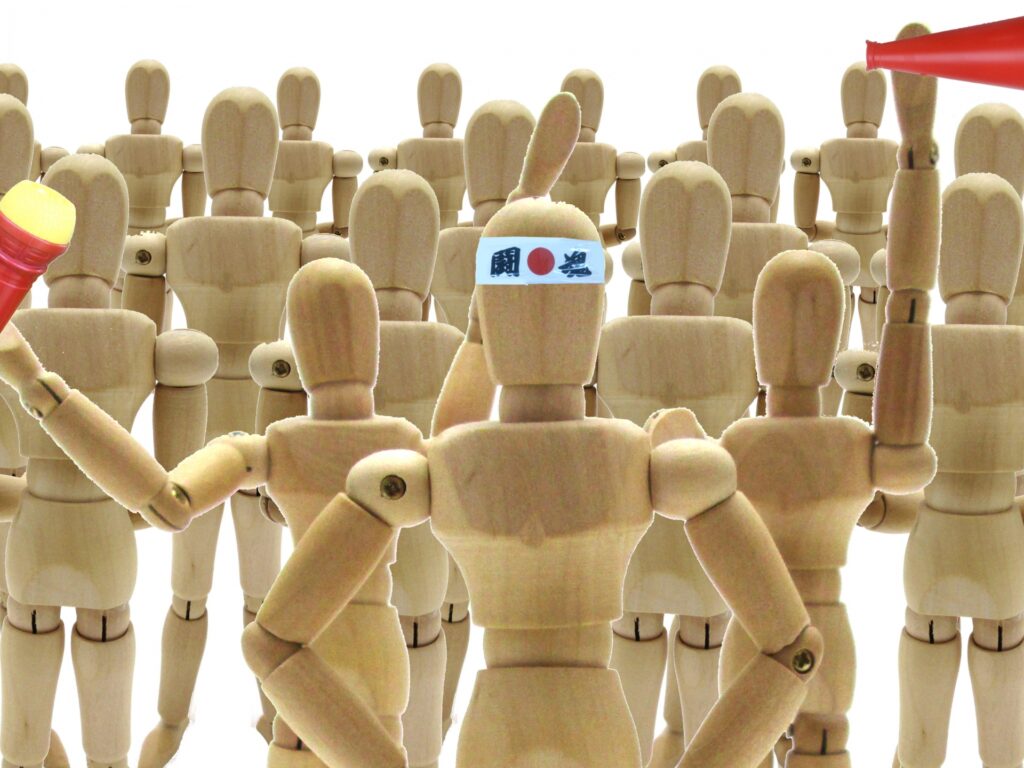
当時は、学生運動が盛んで、学校のキャンパス自体が過激な学生運動の舞台となっていて、ロックアウトされ、授業がほとんどなかったこともある。
趣味のクラブに入ろうと思って部室を訪ねても、そこは左翼思想のたまり場で、タバコの煙が舞い、アルコールの匂いが充満し、なおかつそこにいた人も、ヒッピーのような姿で、訳の分からない理論を話していた
田舎から出てきた者にとっては、そこはきらびやかだが、軽薄で、胡散臭いものがあったのである。
私は文学者として世に出たいという夢をもっていたので、とうていこうした退廃的な世界には合わないと思って、それ以後、あきらめた。
その後、夜間部の第二部の同人雑誌のグループに入ることになったのだが、それは私と同じような田舎出の泥臭さをそこに感じたからである。
昼間は働いている人が多いので、考え方も社会人らしく、現実的で、しかも地に着いた印象を受けた。
同人雑誌の会合もあったが、そこでは私の知らない知識や議論が多く、喫茶店の隅の席に座って議論などをただ聞いていただけだった。
なぜあのように、熱く語れるのだろうか、そのことに驚いていたことを覚えている。
なので、基本的には大学のキャンパスに少しばかりの居場所を見つけたものの、アパートに帰ると何もすることがなく、隣近所の眼を気にしながら生活していた。
地方から出てきた者にとっては、隣近所の人間関係も希薄なので、隣の人が何をしている人かもまったくわからない。

それこそ俳聖の松尾芭蕉が詠んだように、
秋深き 隣は何を する人ぞ
の世界である。
この芭蕉の俳句は晩年の作らしく、死の境地、その寂しさを詠んだという解釈があるようだ。
江戸時代は、隣近所の関係は濃密で、それこそコメを貸したり、ケガをすれば看病したりするほどだったので、確かにこの芭蕉の句には何等かの意味があるだろう。
もちろん、人間関係が濃密だったというのは、江戸の町を舞台にした時代小説や映画などのイメージもあるだろうが、犯罪や反乱を防ぐための「五人組」などの連帯責任を負わせていたので、「江戸砂漠」ではなかったことだけは確かだろう。
落語でも、大家さんと住人の滑稽なやりとりは、そうした濃密な人間関係が背景なったからこそである。
いずれにしても、芭蕉の俳句には、人間関係の希薄さというよりは、人生を生きて来て、何もなく晩年を迎えたという感慨があるに違いない。
芭蕉は、家庭を持って生きたというイメージはあまりない。
弟子を教え、そして、パトロンのところを訪ねながら、生活したという、それこそ高等遊民のような印象がある。
その意味では、隣人が何をしているかわからない、という感慨は、人間としての当たり前の家族を営んでこなかったということの孤独感を表しているのかもしれない。
隣人とは妻であり子供であるといった感じだろうか。
人間の人生は裸で生まれ、裸で死んでいくというものだが、それは本質的な部分ではそうであっても、総体からみると、家族や親族という人間関係の環の中で、遺伝子DNAを過去から受け継ぎ、それを子や孫に託していくというサイクルがある。
植物世界も動物世界も、そうしたサイクルがあるからこそ、子育てをして、それから死の世界へ還っていく。
人間は自我という個人主義をもつことによって、そうした歴史性や社会性というものに所属した自分であるという意識が希薄になってしまったと言えるだろう。
それが孤独死の一端の原因である。
そのことを考えれば、人間の家族性や社会性を回復させてくれる「宗教」は、ほかの何よりも重要なものかもしれない。
私自身、地方から上京して半世紀近くになるが、身近な隣人や友人というものが希薄であると感じることが多い。
このままでは、孤独死や孤立死というものをただ待っている状態になってしまう。
「宗教」がもつ本質、心の安寧をもたらす絆、そして自分を超えた存在を知ること、これこそが今必要なものではないか。
そう思うようになっている。
(フリーライター・福嶋由紀夫)

