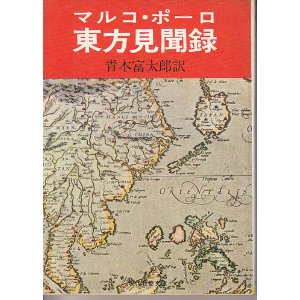
ヨーロッパに、黄金の国ジパング(日本)を初めて紹介したのは、マルコ・ポーロの『東方見聞録』である。
この本によって、中世ヨーロッパの人々は東洋の神秘の国にあこがれを抱き、その一人であるコロンブスは大西洋からインドや日本へ旅立った。
その結果、大航海時代を通じて西洋文明と東洋文明の本格的な邂逅(かいこう)がなされ、コロンブスはアメリカ大陸を発見するということになった(実際はアメリカ大陸を発見したのはコロンブスではないが)。
そのように、ヨーロッパ社会に衝撃を与えたマルコ・ポーロの『東方見聞録』だったが、かなり内容に間違いや現実離れした記述があるために、マルコ・ポーロは実際には中国まで行っていないのではないか、という疑惑がかなり前からあった。
この背景には、この『東方見聞録』がマルコの直接著述したものではなく、マルコがベニスとジェノヴァの都市間戦争で捕虜となって獄舎に囚われた時、そこに居合わせた同じ捕虜の作家(斜塔で有名なピサの出身)が話を聞き出し、それを出版したという経緯がある。
マルコは記憶を元に話し、またメモ書きをしたノートを取り寄せて、この東方への大旅行記を語ったのだが、もちろん、それには記憶の衰えによる間違えもあっただろう。その上、この聞き書きをした作家は、当時の通俗作家だったので、マルコの話をそのまま聞き書きしたのではなく、読者に面白がって読んでもらうための想像や冒険を付け加えた。
その意味では、現在の事実を元にしたノンフィクションのようには受け止めることができないのは言うまでもない。あくまでのマルコの話を元にした小説、冒険譚と考えた方がいいだろう。
ただ、そうであっても無視できないのは、この旅行記の動機になった部分、キリスト教と当時の中国の元王朝との関わりである。マルコの中国への旅のきっかけは、最初は父のその弟の二人だけが商品を携えて向かっていったことから始まる。
二人は紆余曲折を経て、当時の元のフビライ・ハーンの宮廷に招かれ、ローマ法王への手紙を渡す使節に同行して行くように頼まれた。その手紙の内容は、「キリスト教の教理に精通した百名の人を派遣してもらいたい」というものだった。
「その人たちは七つの学芸に精通し、大ハーンの領土内にいる学者たちに、公明正大な論議で、キリスト教の信仰が、他のいかなる信仰よりもすぐれ、しかも明白な真理の上に立つものであり、タタール人の神々や、家庭で礼拝される偶像は悪霊以外の何ものでもなく、これらを神として信仰するのはあやまりだ、と説明できるだけの人物がほしい」(青木富太郎訳『マルコ・ポーロ 東方見聞録』教養文庫)
これは本文に入る前の序説なので、ポーロ本人ではなく、ピサの作家が書いたものになるが、ふつうならば少し信じられない話という印象を持つだろう。フビライがキリスト教に本当に関心があったのか。日本の戦国時代の武将(キリシタン大名)のように、貿易をするための方便ではなかったのか。
おそらく、ピサの作家がこのようなキリスト教へおもねるようなことを書いたのは、当時のヨーロッパのキリスト教社会への配慮があると見ていい。ただ、まったくのデタラメかというと、そうではなく、フビライからの手紙はあり、そこにキリスト教の司祭を派遣してほしいということは書いてあった気がする。なぜなら、モンゴルの祖であったチンギス・ハーンの部族(ケレイト族だったか)は、ネストリウス派の信仰を持っていたという話を読んだ記憶があるからだ。
ネストリウス派のキリスト教は、唐の時代に景教と呼ばれ長安で景教の寺(大秦寺)を建て、当時大流行したことは、よく知られている(大秦景教流行中国碑)。それが事実であれば、シルクロード経由で来た景教の僧侶が途中、布教し、モンゴルの人々にキリスト教が伝えられていた可能性があるだろうと思うからである。
その後、マルコの父とその弟によって手紙がローマ法王に届けられ、結果的に二人の司祭を派遣してもらことになった。そして、マルコたちは、フビライの手紙に付け加えられていたエルサレムのキリストの墓に供えられた秘油をもらってほしいという願いを実現し、マルコの父は子供だったマルコ・ポーロを連れて元へと再び旅立った。
ただし、この二人の司祭は、中継地点でイスラム教の大軍がキリスト教徒を殺害している話を聞いて震え上がり、派遣された騎士とともに、マルコたちに手紙を託して逃亡した。もし、この逃亡した司祭が元の国まで到着したどうなっただろうか。
歴史にイフはないけれど、ふと大航海時代以前に、アジアにキリスト教が伝えられ、儒教の教えと混じり合って、新しい東洋文明の礎が生まれたのではないか、と思ったりする。
(フリーライター・福嶋由紀夫)

