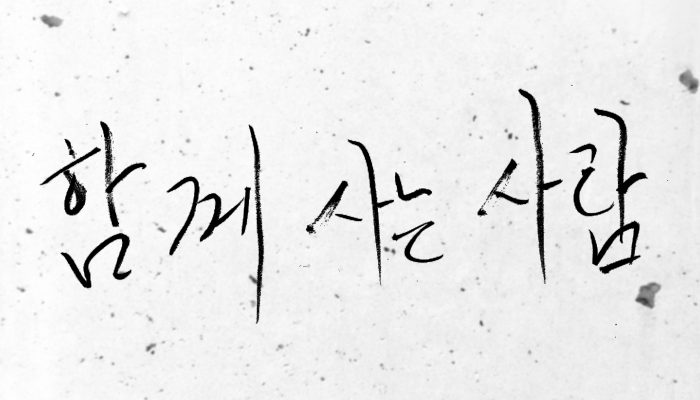
黄七福自叙伝09
「ああ祖国よ 我れ平壌で叫ぶ時 祖国は統一」
第1章 祖国解放までのこと
友禅工場で働いたころ
日々仕事に追われ、その仕事をこなすのが精一杯だったが、日本人が感心するほどに真面目に一生懸命やったから、評価も次第に高まってきた。
友禅の色合わせは、一日中やる仕事でもなかった。赤でも一つの色で赤は出ないし、ボタンとツツジの色も違うから、そういう色を微妙に感じ取り、それぞれに合う絵の具を選び出すという仕事だった。
休みの日は加茂川を散歩して息抜きをし、疲れをとった。
不良少年狩りというものがあって、公園に座っていると、刑事がやってきた。
「なんでここにいるのか」
「きれいな空気をすいにきました」
「体、どこが悪いのか」
と、私のワイシャツのボタンをはずそうとした。感情が高ぶり、
「あんた医者か」
と、抵抗し、押し問答になった。
警官も顔をしかめるほど、私は理屈っぽい性格だった。
時には「朝鮮人は嫌いだ」といわれるほどだった。幼い時であれば、「この子は生意気だ」と思われたかも知れない。
自転車の二人乗りは違反だったが、戦争が激しくなり、燃料が少なくなって、二人乗りを許可したことがあった。 “許可”の新聞記事が載ったその朝、友達を乗せて交番の前を通った。
すると、案の定、警官がピピーッと笛を鳴らして
「止まれ」
「おまえ、なんで二人乗っているか」
「いやいや、今日から二人乗りしてもいいようになったから」
「なに」
警官はまだ新聞も読んでいなかった。新聞で”許可”を目にし、不問ということになった。
そんな調子で、警察官には常に抵抗した。
が、日本人に化けようという気持も大いにあったから、口では日本人そのものを装った。
まるで二重人格そのものだった。
祖国の独立を願ったこと
日本での朝鮮人に対する差別は激しかった。そうした差別を避けるためには、日本人に見られることが手っ取り早い方法だった。
だから、日本人らしく見られようと努力した。しかし、腹の中は、わが祖国がどうしたら独立できるか、の思いでいっぱいだった。
国がどうしたら独立できるかと、心の中は日々悶々としていた。
私はもともと過激な性質だったから、独立のために必要なら、爆弾でも投げてやろうという気持がいつもどこかにあった。
私の身近なところに独立闘争に捧げる指導者がいて、「国のために、爆弾投げてこい」と言われたら、やっていたかもしれなかった。三つ子の魂百までというが、今でもそういう気持がある。
朝鮮人に対する差別に我慢できず、時には死んでもどっちでもええわと思うやけっぱちの気持になって、いつでも決起できるという心の準備もできていた。
が、その当時は、そうした気持があっても、実行に移すことは困難だった。
心の中では祖国の独立を願う気持が強く、祖国の独立のために何か組織をつくりたいという気持もあったが、監視が厳しく、簡単にできる状態ではなかった。
それに、日々の生活では日本人になりきろうと努力していたから、同胞とのつながりはほとんどなかった。朴烈が爆弾を投げたなどの話も知らなかったし、そんなニュースを目にし、耳 にしたこともなかった。

