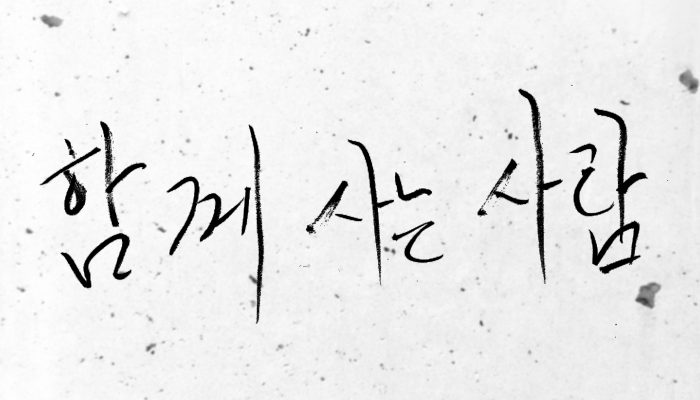
黄七福自叙伝24
「ああ祖国よ 我れ平壌で叫ぶ時 祖国は統一」
第2章 祖国が解放されたこと
朝連が結成されたころ
金天海が出獄して五日目の十月十五日、東京の日比谷公会堂に全国の代表約五千名が参集し、権赫周(権逸)の結成経過報告を承認して満場一致をもって「在日本朝鮮人連盟」(朝連)を結成することになった。
そこへいたるまでの経過は、九月十日に「在日本朝鮮人連盟中央準備委員会」が結成され、委員長には米軍との折衝を考えて、趙得聖(白川一宇)が就任し、副委員長には日本側によい権赫周(権藤嘉郎)と共産系の金正洪(清水武雄)の三名が選任されていた。
ところが、第二日目の十六日に、会場を両国公会堂に移して開会されたが、開会を前にして会場には『朝鮮民衆新聞』がばらまかれ、そのなかには「親日派民族反逆者を組織から葬れ」などの煽動記事が満載されていた。
そして、会場にのぞんだ右派の指導者たちを、左派の青年隊が公会堂四階によびつけ、殴打暴行を加えて監禁してしまった。
そうして会議は、左派の指導者である金正洪によって進行され、その役員陣は左派とその同調者によって、一方的に独占してしまった。こうして朝連の中央役員陣は一夜にして左派一色に塗り替えられてしまったが、その背後にはおそるべき共産派のいわゆる板橋会議の陰謀が隠されていたのである。
板橋会議での陰謀というのは、十五日の経過をみた左派陣営が、同日夜、板橋の李秉哲宅で緊急陰謀会議をもったことである。参加者は、金斗鎔、朴恩哲、曺喜俊、金正洪、韓徳鉢、金民化、金薫、朴成光、朴興奎、朴斉範、李秉哲、呉宇泳など約二十名であった。そして、次のことを決めたという。
①第二日の開会の前に、会場で朝鮮民衆新聞とビラをばらまく。
②その間に壇上にいる幹部を楽屋裏へ呼び入れ、李秉哲の指揮する青年隊が権逸だけを四階に拉致し、その状況を他の幹部たちにわざと見せて反撃をおさえる。
③会議の司会は金正洪が行ない、活動方針の討議の中で、大衆を「祖国の解放と独立達成」「親日派民族反逆者の徹底粛清」の興奮にもりあげる。そして金天海同志の演説を行う。
④各同志と青年行動隊は、会場に散在して声援と拍手で、大衆の行動の統一をはかる。
⑤宣言、綱領、規約はそのままとし、委員長は趙得聖、副委員長は尹槿、金正決とし、中央常任のメンバーも大体予定しておく。
こうして第二日目の会議は、その筋書きどおりに運ばれたのである。
この会議には金天海と宋性徹は参加しなかったが、金斗鎔、朴恩哲は最初から最後まで臨席し、その討議と決定を指導したといわれている。
この陰謀的なやり方は、共産党の大衆団体を指導する典型的な方式であり、その後も朝連の中央委員会や大会には、必ずこのような事前の党員会議がもたれたという。
なお、この陰謀の主となった李秉哲は、一九四六年十二月二十日の「生活擁護人民大会」、いわゆる首相官邸暴力デモ事件の首謀者として、軍事裁判の判決を受け、共謀者らとともに韓国へ強制送還された。
権逸の回想のこと
板橋での陰謀会議の標的となった権逸は、その回想録の中で、そのときの恐怖を次のように回想している。
翌十六日、総会は場所を両国公会堂に変えて続開された。私は気がすすまなかったが、申君の勧誘にしたがって会議に出席した。
会議場に入ってみると事態は心配していた通りであった。全国から集まった代表たちに、金桂淡(金天海直系の部下)が発行した謄写版刷りの『朝鮮民衆新聞』創刊号が配られ、そこには「XXXなどを徹底的に葬れ!」などという激しい煽動記事が満載されていた。
場内の雰囲気は今にも爆発しそうに騒がしかった。私は、これはいけない、と京都帝国大学教授である李哲在博士(越北)とともに会場を出て、近くの隅田川河畔に行った。
「本当に大変なことになりました。どういう考えでこんなことをするのか分かりません」と私は李博士に話しかけたが、李博士もやはり「朝鮮人はこれで困る」と言いながら深刻な表情をされた。
このとき、何人かの青年が私たちに近づいたかと思うと、そのなかの一人が「ちょっと話があるから行こう」と私を引っ張った。私が引っ張られて行ったところは、総会場である両国公会堂の四階であった。そこには、既に康慶玉、李能相、朱基栄等の同志が閉じ込められていて、 恐怖に震えていた。
共産主義者たちはとうとう白昼テロをやってのけたのである。罵倒と泣き声が乱れ飛ぶなか で、拳と靴、棒切れが容赦なく私を襲った。
私は、生まれてはじめて経験する暴挙の前になす術もなく、私の運命を彼らの残忍な手にゆだねるほかなかった。頭と顔が裂け、血がほとばしり瀕死の状態に陥った。
「こいつを、外にほおりだせ!」と叫ぶ声がかすかに聞こえてきた。混沌としている意識のなかで、この叫びを聞いた私は心臓が止まる思いだった。四階の窓から外へほおり出されたらすべて終わりだ。
私は何か叫びたい衝動にかられたが、声にならなかった。そのとき、怒鳴るような声とともになだれこんできた人々がいた。趙得聖(当時の朝連準備委員長)と李康勲の両氏が青年たちを動員して駆けつけてくれたのだ。
万一、この時、この人々が来てくれなかったら、私の命は救われなかったかも知れない。今でも私は生命の恩人であるこの両氏に深く感謝している。
今日の彼ら左翼の団体である『朝総連』はこの『朝連』を母体にしたものであり、『民団』はこのとき追いだされた私たちが、朝連に対抗するため、「建同」の過程を経て翌年十月三日に発足させたものである。
在日同胞の左右の葛藤がこのようであり、民族陣営の出発がこのように険難であったから、その運営の過程が如何に困難であったかは想像がつくであろうと思う。よく、民団の人たちは「民団の歴史は茨の受難史であり、生残るための歴史である」というが至言である。

